 角打ち資料集
角打ち資料集  角打ち資料集
角打ち資料集 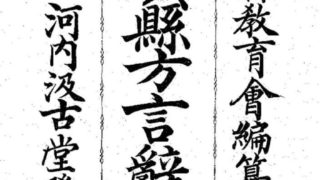 角打ち資料集
角打ち資料集 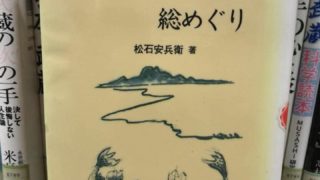 角打ち資料集
角打ち資料集 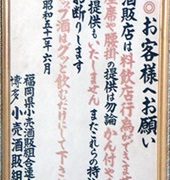 角打ち資料集
角打ち資料集  角打ち資料集
角打ち資料集  角打ち資料集
角打ち資料集  角打ち資料集
角打ち資料集  角打ち資料集
角打ち資料集  角打ち資料集
角打ち資料集  角打ち資料集
角打ち資料集  角打ち資料集
角打ち資料集  角打ち資料集
角打ち資料集  角打ち資料集
角打ち資料集